カリキュラム紹介
私たちは、子どもたちの知的好奇心を引き出し、自ら学び・考える力を育むことを目指しています。
どの教科も大切に、バランスのとれたカリキュラムを実施しています。
なかでも本校では、理数系の学びや国際性を育てる英語教育に特に力を入れています。
英語
Respect independent thinking and self-expression, and convey one’s own feelings and opinions in English.

本校は、1945年のアメリカからの4人のシスターによる英語教育から始まり、今までずっと続く創立以来のNotre Dame Englishの歴史があります。毎日、必ず英語に触れることのできる「English Everyday Program」を全校で実施し、「あいまいさに耐えて英語を聞き取ろうとする力」を確実に 子どもたちにつけています。
全学年週2回の英語授業は、ネイティブ教員と英語専科、担任も交えながらのティームティーチングです。オーセンティックな教材(ネパール校との文通など)を通して、自分の思いや考えを英語で伝える経験を重ね、真のコミュニケーション能力を育んでいます。
Pick up!
TOEFL Primary受験で、国際基準の英語力を身につける
4・5年生は全員が、国際的な英語テスト「TOEFL Primary Step1」のリスニング・リーディングに挑戦しています。その結果が【CEFRレベルA1(英検3級相当)】と評価され、中学卒業相当の英語力をすでに身につけつつあります。
また、ライティングでは【英語の音韻認識(Phonological Awareness)】の習得にも力を入れており、音と文字の構造的理解を通じて、正確な英語の読み書き力を育てています。英語での思考力と表現力を、日々の授業でしっかりと育んでいます。

9分×5日で変わる。「English Everyday Program」
週2回の英語授業に加えて、毎日9分間の短時間英語学習を全学年で実施しているのが、English Everyday Programです。
短時間でも毎日継続することで、リスニング・リーディング力や語彙力が飛躍的に向上。この取り組みの最大の特長は、インプットとアウトプットを日常的に繰り返す学習設計にあります。
「聞く」「わかる」「伝えられる」を日常にすることで、英語を“学ぶもの”から“使えるもの”へと変えていく。そんな未来を見据えた英語教育が、子どもたちの毎日に息づいています。

| Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ND English Time(module) | ○ | – | – | – | ○ |
| English Morning Time | – | – | ○ | ○ | – |
| English TV Broadcasting | – | ○ | – | – | – |
算数
未来を切り開く「知的好奇心」と「粘り強さ」

ノートルダムに入学してくる子どもたちは知的好奇心にあふれています。ノートルダムでは、そんな子どもたちの興味関心を損なわず、さらに「ねばりづよい姿勢」を身につけてもらうことを目標にしています。
長年続く伝統の計算大会・文章題大会では、目標に向けた継続的な練習を通じて、確かな基礎力とやり抜く力を身につけます。
日々の授業では、日常生活の問題解決に算数を役立てる学びを通して、生きた算数力を養うとともに、中学入試を意識した抽象度の高い難問にも挑戦します。
本校の教員全体で算数を指導する「全校算数」や習熟度別クラス編成(高学年)といった仕組みで子どもたちをサポートし、たとえすぐに答えや結果が出なくても、試行錯誤を繰り返しあきらめずに深く考えぬく力を育みます。
Pick up!
繰り返しの練習が、自信になる。検定・大会を通じた基礎の定着
本校では、すべての学年で数学検定・算数検定に取り組んでおり、学校として継続的に表彰も受けています。また、希望者には算数オリンピック予選会への挑戦も推奨しており、全国でも珍しい“小学校会場”です。
さらに、校内では毎年「計算大会」や「文章題大会」を開催。毎日の宿題として、本番と同じ形式の反復プリントを約4枚程度繰り返し取り組むことで、「100点を目指して努力する経験」が積み重なります。こうした繰り返し学習によって、計算力・思考力の定着と、「やればできる」という自己効力感を育てています。

「わかる!」をすべての子に。3つの習熟度別クラス編成
算数は、子どもによって「得意」「苦手」の差が出やすい教科です。そこで本校では、高学年になると2クラスを【3つの習熟度別クラス】に分け、それぞれの学びに応じた指導を行っています。
- ユークリッドクラス:教科書の内容を超えた発展的な学習を行い、抽象的思考力を高めるクラス
- ガウスクラス:教科書の内容に加えて応用問題に挑戦し、論理的思考力を養うクラス
- オイラークラス:少人数制の環境で教科書の内容をじっくりと丁寧に学習するクラス
どの子も「できた!」「もっとやってみたい!」と思える授業をめざし、自信と学びの楽しさを積み重ねています。

理科
子どもたちの「ふしぎ」を育てる学びの場

本校では、身の回りの自然や日常のちょっとした出来事に目を向け、「なぜ」「どうして」と感じる気持ちを大切にしています。葉の色の変化、雲の形、音の広がり方の中に見つけた“ふしぎ”を出発点に、観察や実験を通して、子どもたちは自ら学びを深めていきます。
さらに、仲間との対話の中で、自分の考えを伝えたり、考えの違いに気づいたりすることで、学びはより豊かになります。また自分の「気づき」を言葉にして共有するために、思いやりやコミュニケーションの力も育っていくことになります。こうした体験的な学びが、子どもたちの探究心や表現力、そして「知ることって楽しい!」という気持ちを育てます。
自然に目を輝かせ、仲間と対話しながら学ぶ――そんな子どもたちの姿があふれています。
Pick up!
子どもが主役の理科。PBL型の授業で探究力を育てる
本校の理科では、PBL(Project Based Learning)型の学習を取り入れ、子どもたちが自ら課題を見つけ、調べ、話し合い、発表まで行うことで「主体的な学び」を実践しています。
たとえば、「周期が1秒ぴったりになる振り子を作ろう」や「おいしい焼き芋を作るためにはどんな工夫が必要」といったテーマにグループで挑戦します。
日常の“ふしぎ”を入り口に、探究心と創造性を育んでいくことで、知識の定着だけでなく、【非認知能力(協働・粘り強さ・表現力)】の成長にもつながっています。子どもたちの「もっと知りたい!」という気持ちを最大限に引き出すことができるのです。
目で見て、手でふれて、「ほんとうだ!」を積み重ねる理科の時間
理科室の前には、「サイエンスコーナー」というスペースがあり、昆虫や水生生物を飼育しています。子どもたちは日常的にこのコーナーで「命と向き合う学び」を体験しています。さらに、理科室が2教室、顕微鏡が2種類、1人1台完備されており、いつでも“見て・さわって・感じて学ぶ”ことができる環境が整っています。
また、本校が所有する自然体験施設「山の家」では、各学年で理科の授業と連携したプログラムを実施。豊かな自然の中に身をおいて、教科の枠を超えて総合学習とつながる学びを展開しています。こうしたリアルな体験を通してこそ、「理科って面白い!」「もっと知りたい!」という気持ちが自然に芽生えます。

国語
学力の土台を育てる「読解力」と「対話力」

「伝え合う」ことができたとき、つながりが生まれ、新たな発見があります。子どもたちに、自分の思いや考えを言葉にして、「相手に伝えるって楽しい!新しい考えを知るっておもしろい!」と思いが湧くようなプロジェクトを実施したり、全学年を通して段階を踏んでいきます。
- 「ND読書100選」
たくさんの表現や考えに触れてもらえるよう、小学生に読んでほしい本100冊を監修した「ND読書100選」を全児童が持ち、良書に親しむように工夫しています。 - 漢字学習
漢字大会と漢字検定を全校で実施。繰り返し練習することで定着させます。 - 習字
硬筆大会・書初め大会を行い、丁寧に書く習慣を身につけます。
社会
現代の社会問題に向き合いながらはぐくむ「探究心」と「考える力」

「社会科って面白いと思わせたい!」がノートルダムの社会科のスタートです。
子どもの心に“なんで?”が芽生えると、自分からもっと知りたい!もっと考えたい!そして、もっとみんなと分かち合いたい!と、学習意欲が膨らんでいきます。
タイミングを合わせてプロジェクト型の課題(現代社会が抱える問題等)をひとつふたつ投げかけることで、子どもたちの社会的思考は無限に広がっていくのです。
また、中学受験を見据え4年生からカリキュラムを前倒しします。4年生後半から日本の地理・産業の学習を始め、5年生の後期から日本の歴史に入り、6年生の12月までにカリキュラムをほぼ終えます。日本の産業や歴史、公民の分野では、より深い内容取り入れ、中学受験に対応できるようにしています。
音楽
感性を磨く音楽教育

創立以来、感性を磨く音楽教育「感じる心」の育成を大切にしてきました。
「歌唱」「器楽演奏」「創作」と、作曲編曲者の意図や思いを享受し自分なりに考えを深める「鑑賞」、中でも「器楽演奏」では、低学年でのヴァイオリン学習、高学年の器楽合奏や箏の学習等で本物の楽器を演奏します。
また、プロの音楽家の演奏を聴く鑑賞会を実施しています。
未来に生きる子どもたちの感受性を高め、音楽を楽しむ心を養います。
図画工作
生み出す喜び、こだわるおもしろさ

図画工作では子どもたちが試行錯誤を繰り返しながら、作品を生み出す喜びを実感します。
カリキュラムは題材選びから使用する画材や材料の選定まで、一つひとつにこだわったものを作成しており、子どもたち一人ひとりの「つくりたい」という気持ちを尊重し、ものづくりの楽しさや表現の奥深さを学べるものとなっています。
- 京都府立植物園での写生会
50年以上続く伝統行事で、本物の自然と向き合いながら作品を仕上げていきます。 - 美術展(年度末)
校舎が美術館に大変身。子どもたち一人一人のこだわりや独自の視点が表現された力作が並び、その成長を子どもたち自身が実感できます。
生活・総合学習
多様な体験を通して、子どもたちが考え、深め、発表するプロジェクト!!

「学年テーマ」「山の家学習」「礼法」の3本柱を中心にカリキュラムをつくっています。
- 学年テーマ
低学年は身近な家族や学校周辺、中学年は京都から日本へ、高学年は日本から世界へと範囲を広げてテーマを決め、個人・グループ・チームなど様々な形態で学習を進め、他学年や保護者、社会で関わる人に向けてアウトプットするプロジェクトに取り組みます。
| 1年生 | 大茶会 |
|---|---|
| 2年生 | 野菜づくり・地域プロジェクト |
| 3年生 | 京都大研究 |
| 4年生 | 稲作・環境学習 |
| 5年生 | 平和学習 |
| 6年生 | ディスカバリー |
- 山の家学習
里山での体験学習を中心にした山の家学習では、畑作・稲作体験、自然観察、ものづくりなどに取り組み、原体験を積みます。 - 礼法
各学年、年間3回学年担任指導の礼法学習に取り組みます。校内のお茶室を使い、段階的に盆略点前をマスターし、本格的なお茶席でのおもてなしも体験します。
また、生活・総合学習では、さまざまな体験学習を通して、徳と知を身につけた社会人の育成を目標としています。
体育
「楽しい」が学びのきっかけに!運動から踏み出す未来への第一歩

本校の体育では、体を動かすことの「楽しさ」を大切にしています。
子どもたちは、走る・跳ぶ・投げるといった基本的な動きを通して、できた喜びを増やし、難しい課題に挑戦する意欲、仲間と協力する力を育んでいます。
運動を「楽しい」と感じる体験は、自ら進んで取り組む姿勢や体力づくりにもつながります。体育の授業を通して、身につけた力は、将来への学びや生活の土台となる大切な力です。
今日も子どもたちは、元気いっぱいに未来への一歩を踏み出しています。
家庭科
家庭生活をより豊かにする実習実践!

家庭科では、実習実践を数多く取り入れて学習を進めています。
自立への確かな足がかりとなる生活力を育てるために、まずは家庭生活における課題に関心を持ち、自らその解決を目指して工夫できるように心がけて、子どもたちに働きかけます。
知識技能の習得はもちろんのこと、実践につながる力を身につけること目指しています。
実践の一例
- 5年生:味噌仕込みから給食の献立決め・出汁について・食礼での実習
- 6年生:一食分の献立作り(献立から買い物、お弁当作り実習、会計まで)
宗教
神様からのメッセージを受け止めて考える、自分の生き方と行動

小学校は、人間を超える大きな力、命に触れる大切な発達段階です。日常生活での様々な体験と、イエス様の教えを通して、自分はどのように生きるか、対話しながら考えを深めていきます。
人のために生きる喜び、そして周りの人と喜びや悲しみを分かち合うことの大切さを実感できるように努めています。
- 朝・帰りの祈り
- 授業前の祈り
- 食前・食後の祈り
- 宗教放送(校内テレビ放送での宗教的な内容の講話)
- 聖母月のミサ・集い
- ロザリオの祈り(10月中)
- 修養会(6年)
- 死者月のミサ・集い
- クリスマスの集い(クリスマスタブロー)
先生の声
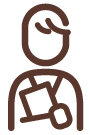
ノートルダムの学びの根幹にあるのは、「ホンモノとの出会い」を通じて育まれる深い思考力です。
英語では、ネイティブ教員との対話やグローバルな教材によって、世界につながる表現力を磨いていきます。
算数・理科では、実験や探究活動、習熟度別の挑戦を通して、理数的な考え方を楽しく身につけていきます。
私たちは、どの教科でも「実感のある学び」「体験をともなう学び」を大切にしています。子どもたちはそこで得た感動や発見を、自分の言葉で語り、考え、表現する力へと変えていきます。ノートルダムは、自ら学び・考える力を兼ね備えた、未来を切り拓く子どもたちを育てます。

